|
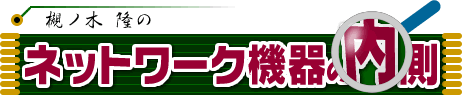
第3回:IEEE 802.11b対応無線LANカード(前編) | ||||||||||||||||||||
|
第3回目は、無線LANカードの内部構造をご紹介したい。今回はアイ・オー・データ機器が発売しているIEEE 802.11b対応無線LANカードであるWN-B11/PCMである。 ■主なハードウェア的スペック 最近、無線LANは非常に幅広く利用されるようになっており、その価格もカードが1万をきるのが当たり前になりつつある。今回取り上げるB<>WN-B11/PCMも、筆者が昨年7800円とかで入手したもの。スペック的にはIEEE 802.11bをサポートする、CardBus対応の無線LANカードである。128bitのWEPに対応している点も含めて、ごく一般的なスペックのもの。Wi-Fiの認定は受けてないが、同社のWebサイトで他社製品との相互接続性に関するテスト結果を掲載するなどしており、まぁ事実上問題はない。実際筆者のところでも、使っていてそれほど問題はなかった。 外形寸法は、カード部はPCカードTypeIIサイズである85mm×54mm×5mm程度。アンテナ部はちょっと盛り上がっており、長さは25mmほど、厚さは7mmほどになる。このアンテナ形状は割と良く出来ていて、アンテナ部を左右でつまんでも、上下でつまんでもカードを引っ張りやすい。アンテナの端にはLINK状態を示すLEDが埋め込まれている。個人的には、LINK以外にACTのLEDも装備してほしいところだ。ちなみに裏面はフラットになっており、余分な突起がないのは助かる。
■内部構造(分解編) さてPCカードの内部を見てみることにしよう。アンテナ部の裏側に4カ所の爪があるので、これを緩めるとアンテナ部のカバーが外れるが、これを外しても、実は何も起きない。内部のアンテナ部の先に、何かしらの金具を取り付けるパターンとスペースが残されているあたりを見ると、元々はここに外部アンテナ用コネクタが取り付けられていた、もしくはその計画があったようだ。つまり外部アンテナ取り付けのために簡単にカバーが外れる構造のようだ。 一方本体ケースの方は、これはプラスチックのモールドに金属パネルを嵌め殺しにする構造のようである。そこで裏側の金属パネルを無理やり剥がす。同様に表側の金属パネルを剥がすと、内部の基板を引っ張り出す事ができた。中央の金属板はシールドで、このシールドの中はRF(高周波)部が格納されている。つまり基板の裏側はアナログ回路が、表側にはデジタル回路がそれぞれ集約されている形だ。 ところで内部の基板を見てみると、GEMTEKのWL-211Fという型番が目に付く。そこで台湾GemtekのWebページで探したところ、生産中止となったWL-211という製品が発見された。どうもこのWN-B11/PCMは、この製品のOEM供与を受けたもののようだ。ただ仔細にみてみるとスペックが多少違う(インターフェイスがPCMCIAで、またWEPは64bitとなっている)ため、完全に同一のものではないのかもしれない。
■内部構造(構造編) ではいよいよ細かな内部構造に移る。WN-B11/PCMの場合、米IntersilのPRISMチップセットを使って構成されている。このPRISMチップセットには何世代かある。以下に主なところを挙げてみよう。
【PRISM】
【PRISM II】
【PRISM 2.5】
【PRISM 3】
【PRISM Indigo】 厳密に言えば、PRISM II/PRISM 2.5は、ベースバンドその他のチップを何種類か選べる用になっており、合計の製品数はかなりのものになる。今回WN-B11/PCMに搭載されているのは、比較的新しいものも含まれているが、総じて古いチップが多い。まぁコストの面や回路の枯れ方を考えれば順当な選択だろう。
まず802.11bの信号を取り扱う2.4GHzの信号部だ。このブロックの作業は、要するに「送信の際に必要な強さに信号を高める」というもの。802.11は全て半二重方式の通信方式なので、つまり送信か受信のどちらかしか一度に行なえない。で、受信の場合はアンテナからSAWフィルタ(表面弾性波フィルタ:後述)経由で入ってきた信号を、スイッチからそのままRF/IFコンバーターに入れて終わりであり、逆に送信の場合はRF/IFコンバーターから出てきた信号を、必要な電力に高めてアンテナに送り込む働きをする。 次の段は、RF/IFコンバーターである。RFとはRadio Frequencyの略で、要するに2.4GHz帯の信号。これに対してIFというのはIntermidiate Frequency、中間周波数なんて訳すのが普通で、大体これが600MHzである。要するに、2.4GHzの信号を直接取り扱うのは大変なので、一旦600MHzあたりに周波数を下げて、ここで信号を取り扱おうというものだ。年配の読者の方だと、スーパーヘテロダイン方式のラジオとかをご存知かもしれないが、あれと原理は同じである。ここで周波数を600MHz台という(昔はともかく今では取り扱いが容易な)周波数に下げた上で、いよいよ実際の信号の取り扱いを行なうわけだ。 3段目は、I/Qモデム兼シンセサイザである。この段は、実際にアナログでの変調/復調を行なう部分だ。この段は、実際にアナログでの変調/復調を行う部分だ。802.11bの場合、基本となる変調方式は、直接拡散式と呼ばれるスペクトラム拡散(DSSS:Direct Sequence Spectrum Spread)である。これはもともとの信号に擬似雑音を加え、広い範囲の周波数に分散させる方式と考えれば早い。実はこのDSSS自体のハンドリングは、次に続くベースバンドチップセットが担っている。ではこのモデム段は何かという話だが、「もともとの信号」の変調/復調を行うものである。判りやすくするためにこちらを一次変調、DSSSを二次変調と呼ぶ場合もある。ちなみにこの一次変調の方式は転送速度によって変わっており、1/2/5.5/11Mbpsで各々DBPSK(Differential Binary Phase Shift Keying)/DQPSK(DifferentialQuadrature Phase Shift Keying)/4bit CCK(Complementary Code Keying)/8bit CCKが採用されている。これらの変調方式をハンドリングするのがI/Qモデム段の役割である。 4段目がベースバンドチップである。このチップはアナログ/デジタル混合デバイスで、当然アナログ信号の入出力はあるが、周波数が低いため特にノイズ対策も必要なく、この結果表面に他のデジタル部品と一緒に実装されている。(この写真の上側にあるチップ)ここが最終的にデジタル信号とアナログ信号を変換する部分である。DSSSの実装をはじめとする、802.11bの通信制御の要がこの部分だ。 最後がデジタル段である。ここはベースバンドチップと交信しながら、デジタル側の処理を行っている。PCMCIAインターフェイスや、メモリ/フラッシュメモリのインターフェイスもここに統合されている。 以上、大雑把に802.11bカードの動作ブロックの説明を行なったところで、誌面がつきた。個別の説明については次週の後編でお送りしよう。 (2002/03/28) |
|
| Broadband Watch ホームページ |
| Copyright (c) 2002 impress corporation All rights reserved. |










