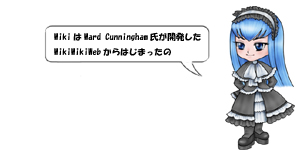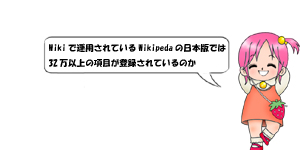|
|||||
その111「Wikiの使われ方」 |
|||||
|
■ Wikiって何? ・Webブラウザのみで操作可能 ・任意にページを作成し、自由に文章を追加/削除/編集できる ・そのページにリンクしている先を自動的に調べられる(逆リンク機能) Wikiは、掲示板が時系列に発言を積み重ねていくのに対し、ある項目に関する情報などを集約したページを作成するために利用されています。また、機能面では掲示板と違って装飾や編集機能が充実しており、変更内容の履歴を残すことも可能になっています。 Wikiはもともと、Ward Cunningham氏が自身の「WikiWikiWeb」を立ち上げるのに作成したものに始まります。“WikiWiki”という言葉はハワイ語で「素早く」「急ぐ」「形式ばらない」といった意味を持っています。 Cunningham氏がこのソフトを公開すると、Wikiはたちまち普及するようになりました。またこれを改良したものや、新規に作成されるものなども多く、今ではどの程度の種類があるか数え切れないほどです。ちなみにCunningham氏が公開した最初のWikiは、WikiWikiWebやWardsWikiなどと呼ばれますが、これの改良型やクローンも同様にXXXXWikiと呼ばれるスタイルが多いようです。 ■ Wikiの使われ方 日本語版の32万という項目数は、例えば約13万項目を収録する小学館の「日本大百科全書」、約3万5,000項目の自由国民社「現代用語の基礎知識2007年版」を大きく上回っています。 また、電子書籍であるマイクロソフトの「エンカルタ総合大百科2007」が約3万8,000項目弱ですから、収録語数の多さがわかると思います。これだけの収録数をフリーで実現できたのは、誰もが自由に文章を作り、編集して公開できるというWikiの仕組みを活用できたから、ということは間違いないでしょう。 もっとも、WikipediaとWiki自体はまったく別物です。Wikiはあくまでもコラボレーションを行なうツールであり、WikipediaはWikiを使って構築されたコンテンツということになります。しかし、Wikipediaをつい、“Wiki”と略してしまいがちなのか、Wiki=Wikipediaを作るためのツール、と誤解されている節がなきにしもありません。こうしたこともあって、「(Wikipediaを)Wikiと略すな(URL)」と呼びかけるケースもあります。現実問題として、WikipediaをWikiと略してしまうと、他のWikiと混同しやすいので、やはりWikipediaはWikipediaと呼ぶのが妥当でしょう。 Wikiはほかにも、さまざまな用途で使われています。一例を挙げれば、「もじら組」などがあります。もじら組はご存知の通り、Mozilla関連の日本語化プロジェクトを行なっている総本山ですが、ここでは以下のような使い分けがなされています。 ・もじら組が発信するニュース:静的HTMLまたはブログ ・利用者が参加する場(フォーラム、トラブル対策など):掲示板およびWiki 管理者などからのお知らせは、ブログシステムの方が管理がしやすく便利な反面、多数の参加者が任意に書き込みおよび編集を行なう場合は難しい点があります。そこで、まず議論や意見交換自体は掲示板である「もじら組フォーラム」で行なわれ、ここである程度収束した情報が「もじら組Wiki」にまとめられるわけです。 ■ Wikiの問題と今後
その反面、いろいろな問題も出てくるようになってきました。例えば、「文字を赤くする」という指定を見ても、各種Wikiサービスで対応が異なります(図1)。また、Wikiサービスごとにプラグイン対応なども異なっていています。後発のWikiサービスは機能強化する方向にあるほか、プロバイダーも差別化の一環としてさまざまな機能を追加しており、結果として互換性はあまり高くありません。 Wiki文法の標準化、という話は何度か出ているようですが、実際に標準化作業が開始されたものは、筆者の知る限りはないようです。その一方、Wikiに「WYSIWYG機能」を搭載しようという動きもあり、実際にプロバイダーの提供するWikiサービスの中には「ワープロモード」などの名称で提供されているものもあります。このあたりは今後も進化していくものと思われます。 また、最近無視できなくなっているのは保護メカニズムです。誰でも自由に編集できるのがWiki本来の趣旨ですが、悪意のある書き込みをどう防ぐかといった点も課題になってきています。これを防止するため、例えばユーザー登録を行ない、書き込みにはユーザー認証を必須にするとか、場合によっては管理者による承認がないと寄稿しても反映されないといったシステムを備えているものもあります。 ただ、こうした対応はWikiが持つコラボレーション機能を相殺しかねない場合もあり、今のところ、妥当な汎用の保護メカニズムに関するコンセンサスはとれていないようです。結果として、各管理者がそのWikiの性質とか運用状態に応じて個別対処、というあたりに落ち着いているようです。 ところで、Wikiの普及に一役買っているのが、「Wikimedia Foundation, Inc.」です。2003年6月に設立されたこの財団は、Wikiを使ってさまざまなプロジェクトを実施しています。 WikipediaもWikimedia Foundationが実施しているプロジェクトの1つとして運営されています。Wikimedia Foundationの目的を端的に言ってしまえば、集合知を実現するということであり、Wikiはあくまでそのための道具でしかないわけですが、使いやすい道具を作ることも目的の実現には重要であり、このために「MediaWiki」というWikiソフトウェアの開発も同プロジェクトで行なわれています。 ある意味、このMediaWikiの仕様や搭載される機能が、Wikimedia Foundationによる事実上のWiki標準化案といってもいいのかもしれません。ただ、その肝心のWikimedia Foundationがこのところ資金的な問題に面しているという話もあり、実際にこうした問題が生じた場合にはWikipediaを含むプロジェクトが継続できるかが危ぶまる可能性もあります。 2007/02/19 10:48
|
| Broadband Watch ホームページ |
| Copyright (c) 2007 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved. |